病気の説明・各論10
自閉スペクトラム・注意欠陥多動症(AS/ADHD) 1
診断の方法・総論
いまだに「発達障害」は専門家でないと診断できないとしり込みしている町医者が多いのですが、冗談もたいがいにしろ、と思います。
宮岡等と内山登紀夫のふたりの医師が「発達障害」について対談(放談?)した本があります。
『大人の発達障害ってそういうことだったのか』(医学書院、2013年 以下正編と略記)
『大人の発達障害ってそういうことだったのか その後』(医学書院、2018年 以下続編と略記)
の2冊です。
ベストセラーで売れているようなので、これを便宜に、これくらいは「普通に」言えるであろうということを、まづは手始めにまとめておこうと思います。
小医が日日の臨床で感じていることは、続編2頁13頁も指摘しているように、発達特性についてよくわかっている医師と、そうでない医師との「格差」が大きすぎる、ということです。しかし、これは患者にとってめいわくです。この「格差」を均(なら)すことが、精神科臨床全体の喫緊の課題ではないかと思います。
正編13頁32-3頁にあるように、ASで1%、ADHDで5%超の有病率があるのなら、統合失調症(0.8%)以上のコモン・ディジーズです。
正編216頁、続編84頁252-4頁が述べるように、発達特性は、精神科医であれば、全員がそれをみぬくことができる技倆をもたなければならないと思います。
- 発達特性は、専門医が診るものではない。決して珍しいものではなくてふつうに見られるものならば、ふつうの精神科医がふつうに診ることができなければならない。
それはあたかも、統合失調症患者における例のいわゆる「プレコックス感」に似たものでしょう。精神科医ならば、統合失調症患者の放つかすかな違和感を敏感に察知できるはずです。なぜ発達特性者にその種の専門的「勘」が働かないのか、その道理がわかりません。
発達特性をこれまで多くの精神科医が見逃してきたことには、しかし、理由があると小医は考えています。
それは「神経症の軽視」です。もっと平たく言うと「患者の声に耳を傾けない」ということです。或は悪しき「傾聴の伝統」です。ふんふんと聞いたふりだけしている慣習です。「内科医としての自覚の欠如」です。精神科医は、内科医にはふつうの臨床実践である診断のための「所見」をとろうという姿勢を怠ってきていました。
くわしく説明します。
精神科医の職場はこれまで多く精神科病院にありました。或は多忙きわまる総合病院精神科外来に。ここからの帰結は、病人しか診ないということです。統合失調症、躁鬱病、うつ病、てんかん、アルツハイマー病など、明確に「病気(疾患)」と認定できる人だけしか相手にしてこなかったということです。
或は投薬で簡単に片がつく神経症圏患者しか。
これら患者の診断にさほど時間は要しなかったことでしょう。ふんふんと聞いたふりをしつつ、さっさと入院させるなり、さっさと処方箋を出すことを考えてさえいれば、大体は事が済んだのです。
たまに長々と話しこんでまとまらないけど、どうも病人ではないような人が紛れ込んでくれば、「妙なヤツが来たもんだなあ」と首をひねっていたのです。或は甘え切ったことをほざく若者が紛れ込んでくれば、「最近の若いヤツはどうもひ弱だ」とか世の風潮を嘆いておればそれでよかったのです。
しかし、こうして、精神科医の「ひとを見ぬく眼力」は、日々おとろえていったのではなかったか? 多くの人がふつうに行き交う、まちなかのクリニックには、上記の職場からは徹底的に締め出されたはずの、真の「神経症」ともいうべき発達特性者の受診ニーズが山ほどあったというのに。
発達特性者の診断には、一定の時間がかかります。「特性があるのではないか?」と最初に疑診してかかる必要があります。続編54頁61-2頁65頁101-2頁に示された通りです。
ふんふん患者のいうことを受身で聴いてばかりいるのではなく、疑診した以上は、医者の方から、あれこれ患者に訊き出して、内科医のように積極的に「所見」をとっていく必要があります。精神科医の「惰性」、「ナマケモノ根性」を捨てていく必要があります。
- 受診者を「普通の人」と眺めていては何も見えない。積極的に「疑う」ことで、受診者から芋づる式に、発達特性をさらに疑う手がかりが、ぞろぞろ出てくる。但し、その前に典型的な精神病の可能性を除外してから。
疑うきっかけとして、何か「いつもの」精神病圏の手ごたえとは違うぞ、というびみょうな感覚が重要だと正編57-8頁61頁は説いています。これはふつうの精神科医ならば、できることでしょう。但し、そのようないつもと手ごたえが違う、風変わりな受診者のどこに注目していくか? 具体的な診断方法がここで必要になって参ります。
しかるに「使える教科書がない」と正編247-9頁は嘆いていますが、これが多くの町医者の嘆きなのかも知れません。
しかし、「世間という書物」を読むために書を捨てて旅に出た、かのルネ・デカルトの精神にならっていえば、DSMを捨て、毎日毎日、「受診患者という書物」をくりかえしくりかえし丹念に読んでいくと、徐々に「発達特性のありか」は見えてきます。診察のアートも純化されていきます。
このアートは磨いて決して損はしないものだと思います。チェックリストに何点あてはまっているから、あなたは発達障害だとかいう、医者の風上にも置けぬ情けない診察(続編254頁参照)ではなく、患者も「これは美事」と納得せざるを得ない、シャーロック・ホームズもかくやとばかりの名人芸の診察を披露することができるようになっていきます。
小医) 「ずばり、あなたはこういうお人柄ですね?」
患者) 「しかし、先生…。先生はどうしてすぐにそうとおわかりになりまして?」
小医) 「あなたのお顔、髪型、服装、持物すべてがそうと教えています」
患者) 「!?」
効率的な短時間診断法がないか、続編125頁は模索しているようですが、小医はこの一年余の経験で診察の手順をかなり「定型化」することはできた自信があります。小医が日日おこなっている具体的な診察手順は、章をあらためて述べます。この「総論」で語るべき事柄はまだ他にもあるので、その記述を先に済ませたいと思います。
まづはWAIS-IIIなどの臨床心理検査の位置づけです。小医が患者から仄聞するところによると、臨床心理検査を経なければ、発達障害と診断できないとか患者に説明している町医者がありました。それでもあなたは精神科医ですか?
- 発達特性の有無は、医者の診断による。臨床心理検査は、診断のための一参考資料に過ぎない。医者は臨床心理検査士に対しては、患者を厳しい目で観察するよう、よくよく指導しなければならない。
続編68-71頁が正しく指摘しているように、WAIS-III検査があくまで参考程度にしかならないことは、じぶんが発達特性を疑った患者さんに臨床心理検査をオーダーしてみれば、自然と体感できることと思います。きれいな「模範的結果」が出ないことのほうがはるかに多いのです。
大事なことはじぶんの診断の目を磨くことではないでしょうか。そして続編242-3頁290-1頁が指摘するように、「診断」という責任を負おうとはしない臨床心理士に、楽観的な目を捨てて、患者を厳しく査定せよという、医者として当り前の指示を出すことが重要でしょう。その時にはじぶんが発達特性を疑う上で根拠とした観察ポイントをできる限り多く臨床心理士に伝えることです。臨床心理士もアマチュアではないので、医者からの情報提供は検査を実施する上で大変参考になると思われます。
検査値の値が問題にならないことは、ADI-RやADOS、CAADIDにおいても同じ。そのことは続編72-3頁にも示されていますが、実際にじぶんが発達特性を疑った患者さんにこれらの検査をオーダーしてみれば、自然に体感されることだと思われます。いったい、いつからか精神科医はじぶんの職業的「勘」を信じる自信を失っているのでしょうか?
AS(自閉スペクトラム Autism Spectrum)やADHD(注意欠陥多動症 Attention Deficit Hyperactivity disorder)を考えるうえで、基本となることは、「正常人」というものがあると仮定して、それとは連続しているということです。正編39頁は大学教員を例に、発達特性をもった人は「たくさんいそう」と言っていますが、医者の会合があれば、ここにもあそこにも、確かに、いっぱいいそうです。(笑)
そこで小医は次のような仮説を立てて、「発達特性」というものを見ています。
(1)うまれつきどう見てもこの子は自閉症やなという子がいるとして、その子の自閉症「濃度」を10とすると、その半分の5でも濃いし、その半分の3とか2でもじゅうぶんに濃く、いわゆる「おとなの発達障害」を疑うべき人の濃度は、0.5から1.8程度なのではないか。そして「正常人」が0.3以下と。
(2)で、この0.5から1.8の濃度をもった人びとの全員が、心療内科や精神科の外来に顔を出すかというと、さにあらず。おそらく半数は絶対に来ない。社会的にきわめて有能で、自信満々であったりする。
この「半数」という数字にはある程度根拠があって、企業内における「パワハラ」や夫婦内における「モラハラ」は、発達特性者の「攻撃型」と「受動型」の組合せが臨床経験上多いので、精神科医は、発達特性者の「全貌」ではなく、「横顔」しか視野に収めていない可能性があるのではないか。
(3)「発達障害」という言葉は、「障害」という言葉自体に問題がある。「障害」という言葉は医学的診断になじまない。それは本質的に、その人に国家的保護を与えるべきかどうかという政治判断にぞくするからだ。
その事情は日本でもイギリスでも同じことは続編74頁に明示されている通りである。医者にできることは、その人にASやADHDという理解の枠組をあたえると、その人がらをよりよく理解できる特性が備わっているかいないか、その事実判断につきる。
医者にできることは「特性の有無」であって「障害というべきか否か」ではない。だから、続編14頁で宮岡等医師が示している「このぐらいだったら発達障害やASDと言わず、…無理に診断をつけなくともよい」という考えに、小医は反対である。特性を見つけ出したことが患者の理解につながり「環境調整をすればよい」という結論に至ったのだから、特性があった事実それ自体を医者が否認することは自らの診療行為を否定したことになるからである。
だから、医者は「発達障害」ではなく、「発達特性(自閉症傾向)」という政治から解放された自然の言葉を使う方が適切なのではないか。つまり「発達特性はこれが軽度あることを認める。しかし障害とまでいうことは差し控えたい」と。
(4)ASやADHDについては、DSMなど世間に流布している一般的な診断基準以外にも臨床的には有意な診断根拠がいくらもあるのではないか。
続編14-5頁で内山登紀夫医師はICDやDSMがASDを記述し尽してはいないと明言しているし、続編89-91頁は「学生時代の欠席日数は所見になる」と述べている。小中高大における不登校歴が、発達特性を疑う有力な根拠となることは、小医をふくめ、多くの発達特性者を診ている医師には、自然に首肯できるところであろう。
町医者の精神科医は、DSMなどを金科玉条とするのではなく、日々の臨床実践のなかで、教科書のどこにも書かれてはいないが、発達特性を疑うべき臨床的に有益な所見(らしきもの)を発見していく必要があるのではないか。それは日々の臨床を行う上でのささやかな「楽しみ」ともなろう。(小医が経験上感じている発達特性を疑うべき所見のいろいろについては、章を改めて述べる。)
(5)性格と「特性」のちがいについて、あくまでも大雑把なひゆに過ぎないが、人をパンにたとえるに、性格はパンの原料となる生地と焼き方に相当する。それによって食感や味が異なってこよう。
「特性」とは、パンの表面に押すパン屋の焼きごての「商標文様」のようなものと考えたい。濃く押されているものからごく薄くおされているものまで、ぜんぶきれいに文様がでているものから欠けて一部しか文様が出ていないものまで、さまざまあろう。
小医は文様が「ごく薄くしか押されていない」或は「欠けて一部しか出ていない」ものが、「おとなの発達障害」を診る上で、示唆的なひゆになるのではないかと愚考している。







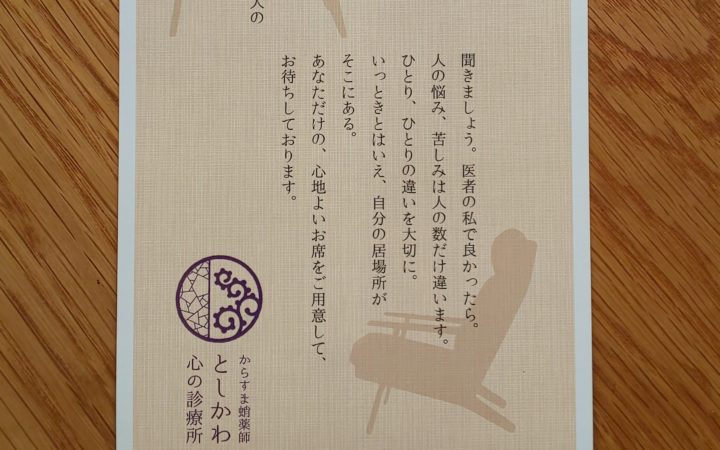


この記事へのコメントはありません。