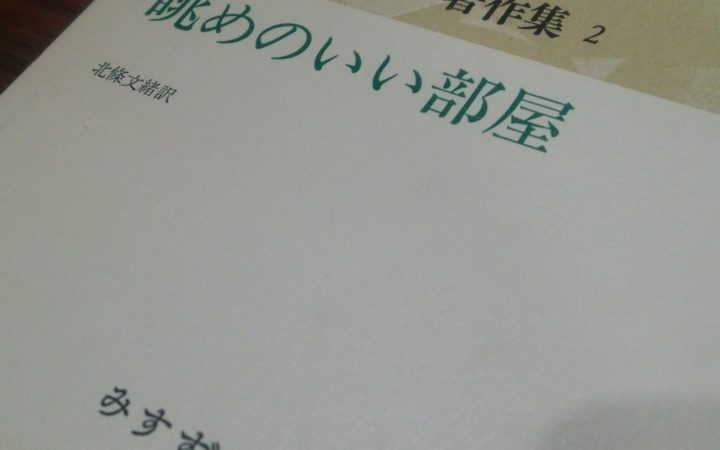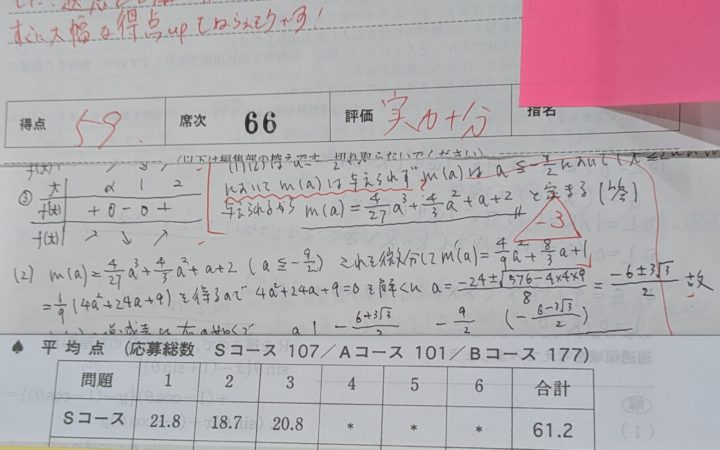懐かしの日本映画劇場 閑居小人
ハイ、みなさん、コンバンワ。きょうは怖い怖い、だけど、面白いナー、そして、なにやら哀しい、けれどもネ、キレイなキレイな映画をご紹介しますよ。
タイトルはね、『恍惚の人』(昭和48年、芸苑社・東宝)。皆さん、御存じか知ら、作家の有吉佐和子。昭和47年、彼女が書いて一大ベストセラーになった小説。その映画化。映画も封切されると、当時大ヒットしました。
だけど、コウコツの人って何かしら?
―お父さん、ポルノや思たら間違いですよ。(笑)実は、これはね、痴呆老人のお話なの。私もいつなるかわからない。(笑)今日びは、こんな言葉つこたらイケマセンって、うるさいらしい。だから、「認知症」とかゆうご時世ですけど、要はボケ老人。そのお話なんです。でも『ボケの人』ではタイトルになりませんわナ。有吉さんは、幕末の歴史家、頼山陽の『日本外史』という本を偶々読んでいて、この言葉をひっぱり出してきた。ヤッパリ、教養ある人は、どこか、ちがいますね。
舞台は東京。物語はね、ある寒い寒い雪の日、映画では雨になっていますけれども、主人公のおんなが、勤め先から電車に乗って家に帰ってくるところから始まる。
この主人公の嫁さん役を演じるのが高峰秀子。デコちゃんですね。もうこの人なくして、日本映画は語れない。五才の時から映画に出ている大スター。おしも押されぬ、りっぱな立派な名女優さんですね。ああ、『二十四の瞳』(昭和29年、松竹)の大石先生。手をふりながら、夫が乗る船と、デコちゃんの乗る船がすれちがうシーン。教え子の少女が唄う「浜辺の歌」。美しくて美しくて、泣けましたなー。戦争はもうたくさんと、日本中の人がこの映画をみて泣きました。世界的にも今も評価が高い名作ですね。
『放浪記』(昭和37年、宝塚・東宝)では作家の林芙美子に扮しました。実物に似てないと当時はずいぶん叩かれた。だけどね、いかにも本物らしい存在感がよう出てましたナー。「花のいのちは短くて、苦しきことのみ多かりき」。学歴もロクにない、ひとりの貧しい女が、はたらいて働いて、くろうして苦労して、作家になる。その姿がよう描けておりました。木下恵介と、成瀬巳喜男。戦後はこの二大巨匠と一緒にしごとをして、モウ数えだしたらキリがない、数多くの名画を残しています。
サテ、そうしたらね、そこにね、お舅さんがやってくる。しかし、どこか容子がヘンなんです。背広とネクタイはしているんだけど、傘もささずにずぶ濡れ。あてどなく、駅前をうろうろしているのを見つけて、ヘンに思った高峰秀子が家につれて帰る。そしたら、家ではお姑さんが倒れて死んでるんですね。だけど、お舅さんは、しらん顔して、お芋をむしゃむしゃ食べているばかり。
ちょっとコワイですね。ホラー映画の趣があります。家族は「おばあさんが亡くなったショックでこうなったんじゃないやろか」と最初は思うんだけど、お舅さんは、すでに老人性痴呆になっていたんですね。一緒に住んでいながら、高峰秀子の夫婦は共稼ぎだったので、それに気づいてこなかった。この辺りも、なんだか怖いですねー。
お舅さん役が森繁久彌。当時59歳。それが84歳の役を演じてる。これが、しかし、ホントウに、ぴったり。お医者さんの目からげんみつに見たら、じつはチョット合わないところがあるかもわからない。だけど、おもしろいのね。このボケ老人役は、森繁久彌に、ホントウに、ぴったりなんですね。
森繁久彌ゆうたら、おもいだすのは、『夫婦善哉』(昭和30年、東宝)。森繁が維康柳吉で、ヤトナ芸者のお蝶が、元宝塚の大スター、淡島千景。ああ、お景さん、キレイだったナー。この女優は、なんともいえない、キビキビ、くるくるした魅力がある人ですね。森繁は、大阪船場の頼りない、ぼんくら若旦那の役に、これも、ホントウに、ぴったりでしたナー。
きょうの映画の監督は、この『夫婦善哉』の監督、豊田四郎。しかし、本作では、心臓を患っていて、ナイショですが、殆ど、じつは監督らしい監督はしていない。数年後に心臓マヒで亡くなられました。脚本は松山善三。木下恵介の弟子で、高峰秀子のじつのご主人ですね。
高峰秀子のダンナ役には、田村高廣。テレビの刑事もの、古畑任三郎で有名な、田村正和のお兄さんですね。お父さんは、バンツマこと、阪東妻三郎。田村高廣の代表作は、あの『泥の河』(昭和56年、監督・小栗康平)ですね。大阪の、戦後の貧しさが残る家庭の、暗い哀しい、しかし、こどもたちが可愛い、いい作品でしたナー。この映画の話をしだすと、とまらなくなるから、もうこれ以上は致しません。サテ、田村高廣のデビュー作は、木下恵介が監督をした『女の園』(昭和29年、松竹)。学業と将来になやんで自殺をする高峰秀子の恋人役ですね。松本清張が原作で野村芳太郎が監督をした『張り込み』(昭和33年、松竹)でも、高峰の恋人役。きょうの映画では、とうとう、年季の入った夫婦になっています。
ほかに、淡島千景と人気を二分した、元宝塚娘役スターの乙羽信子。あと、ほんとに、この人はねえ、昔っからおばあさんの老け役ばっかりしてきている浦辺粂子と、いい役者さんばかりが出ています。これは一千九百七十三年公開の日本映画です。じっくりとごらんなさい。後でまた、お会いしましょうね。
* *
サア、いかがでしたか?
舅から今まで散々いじめられてきた嫁が、下の世話からはじまって、いちばん面倒をみて、とうとう舅の森繁久彌が肺炎で亡くなった後、舅の買った小鳥のホオジロを眺めている、ラストシーンの高峰秀子があわれですね。血のつながったダンナさんや息子のほうが冷淡で、たにんの嫁がいちばんおじいちゃんを愛していた。
この映画で一ばん美しかったのは、つゆの雨の中、森繁久彌が白い花をみつめるシーン。泰山木の花。ぼけて物がわからなくなったように見えても、「美しい」と感じる心は残っているんですね。それに高峰秀子が気づいた。佐藤勝の音楽とあいまって、ほんとうに感動的な場面にしあがっています。私はしらず、なみだがポロポロ、ポロポロこぼれましたヨ。
それでは、次回をお楽しみに、みなさん、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。
(平成24年7月筆)

1 有吉佐和子『恍惚の人』(新潮社、1972年)
インターネット書店「アマゾン」から、古書として1円(!)で買った本書の奥付をみると、昭和47年6月10日に発行して、その3か月後の9月10日には、27刷(!)とあり、爆発的な大ヒットとなったと判る。最終的には総計118刷、約200万部の大ベストセラーとなったということである。タイトルは時の流行語になり、今なお人口に膾炙(かいしゃ)している。翌年には森重久彌と高峰秀子の主演で映画化もされ(芸苑社・東宝。松山善三脚本、豊田四郎監督)、これも大ヒットした。
当時、若者たちの過激な学生運動が終息に向かういっぽうで、日本はすでに、65歳以上の老齢人口が全体の7パーセントを超える「高齢化社会」に、急速なスピードで突入していた。東京都に、老人総合研究所が設立されたのも、その年である。「認知症」問題は、40年以上も前から存在しており、決して今に始まった話ではないのである。
一般に、ベストセラーは、後世の目から見て、読むに堪えぬものが多いが、本書はその例外で、刊行後約40年以上を経た今となっても、読者をして一気に読ましめるちからを有している。
有吉は、6年間もかけて、読書と実地で、老年医学を勉強したのちに、本書を著したという。
じっさい、手にとってみて、けっして損はない、名作だと思う。
本作は、その名のみ言及されて、中身が紹介されること、まれになっているから、ここにあらすじを記しておこう。
立花昭子は、40代後半、有楽町にある法律事務所で、「邦文タイプ」のしごとをしている職業婦人である。夫は、商社につとめるサラリーマンで、この当時にはまだめずらしかった「共稼ぎ夫婦」である。勉強のできる高校2年生の息子が一人ある。東京都杉並区・梅里の一軒家に住まい、庭の離れに、舅と姑が暮している。
物語は、雪のふる年の暮に、姑が中風(脳卒中)発作で亡くなる所から始まる。舅の立花茂造は、妻の病状を認識できず、助けをよぶ適切な行動をとれなかったため、姑は死後4時間以上も経って、発見される。同じ敷地内に暮しているとはいえ、この「二世代家族」どうしは、昭子夫婦の多忙から、「別居」も同然であり、また、姑ができた人であったため、舅の茂造が耄碌(もうろく)していることは今の今まで気づかれないできたのであった。
84歳になる舅の茂造は、すでに死んだ妻の顔も、息子や娘の顔も分らなくなっていたが、嫁の昭子の顔だけは覚えていて、お腹が空けば、ごはんを食べさせて下さいと泣くのであった。昭子の姿がみえないと、家から飛び出し、ずんずん歩いて昭子を探しに徘徊するため、家人はへとへとに疲れてしまう。
孫は、祖父が人間というよりは動物と化しており、「生物本能」から、じぶんを助けてくれそうにない人の顔は忘れても、じぶんにごはんを食べさせてくれる「飼い主」たる母の顔だけは忘れないのだと穿(うが)ったことをいい、この、長年自分の胃腸の具合にかまけて不平をいうだけで他人にはことごとく気難しく冷淡だった舅に、若い頃からさんざんいじめぬかれてきた昭子は、「おお、嫌やだ」と、ふるふるおぞけをふるうのであった。
夫は、じつの父というのに、茂造の介護の手伝いは、殆ど何もしない。
いちどやらせてみたが、茂造は、息子を息子とわからないため、「暴漢が家の中にいるから警察を呼べ」と大騒ぎするしまつで、けっきょく、茂造を近所の「老人クラブ」(今や死語)に通わせたり、夜中に起きて庭で小用を足す茂造の手助けをするのは、すべて昭子のしごとになった。茂造は終始、ぼうっと夢みるような表情で毎日を過ごしている(恍惚の人)。
理解ある職場とはいえ、欠勤が続き、睡眠不足で体力がもちそうもないことから、「老人ホーム」に入れることを昭子は計画するが、介護保険制度のなかった当時としては、「親不孝!」とのたんじゅんな道徳的批難が世間の一般的風潮で、昭子も直接自分の口から夫にそうしてくれとは迫れず、息子からその話を聞かされた夫も首をタテにふらない。
そうこうしているときに、勤め先の弁護士が、いちど相談してみたらと、紹介してくれた厚生省末端の「老人福祉指導主事」からは、痴呆老人を「隔離する」最終手段としてあるのは、「精神病院への入院」あるのみだといわれ、昭子はショックを受ける。
梅雨の季節に入り、茂造をお風呂に入れていた時に、電話が入り、昭子は女学校時代の友人が婦人科がんの末期で危篤だという知らせを受け、茫然としていたら、目を離したわづかの隙に、茂造が浴槽でおぼれてしまった。茂造は、急性肺炎で死線をさまようが、一命をとりとめる。
今までいやだいやだとばかり思っていた昭子は、これで腹が据わり、茂造を生かせるだけ生かしてやろうと前向きなきもちになった。
このあと、茂造は「モシモシ」以外の言葉は話さなくなり、近所の医者の言葉を借りれば、子どもに「戻って」、天使のごとき微笑を見せるようになった。呆ける前はいつも苦虫を噛み潰したような表情しかみせなかった、あの茂造が、である。
茂造は、このあと、秋晴れの午後に、最後の徘徊をして、警察に保護されたが、衰弱はげしく、翌日の夜、下顎呼吸となり、自宅で老衰死する。
タイトルにある「恍惚(こうこつ)」とは、有吉が、幕末のベストセラー、頼山陽(1781―1832)の『日本外史』をたまたま読んでいた時に、「三好長慶、老いて病み、恍惚として、人を識らず」のくだりをみつけて、これから採ったと自ら述べている。
本作は、みぎのあらすじの中に、冷凍食品を利用して一週間の料理を週末に作りまとめする共稼ぎ夫婦の知恵、客にひと言も口を利かないタクシードライバー、あいさつもロクにできず、口のきき方も知らぬ若い大学院生などの話がちりばめられ、今も通じる読み物として、単純におもしろい。
2 有吉佐和子小伝
昭和6年(1931年)1月、和歌山のうまれ。父は、一高東大法科卒、横浜正金銀行に勤めるエリートサラリーマン。母は和歌山の庄屋で代議士の娘。大正リベラリズムの空気を吸った父母から、自由な雰囲気で育つ。父の転勤で、6才から10才まで、ジャワのバタビヤで育ち、日本に帰る。今で言う「帰国子女」である。
有吉にとって、日本は寧ろ「外国」であり、歌舞伎、三味線、茶道をはじめ、伝統芸能に強く魅了される。見た目とは異なり、病弱で、幼いころから読書に没頭した。16歳のときカソリックに入信する。有吉の風貌には、あどけなさを残したところがあり、童女のようだが、身長は165センチと長身。性格は、目上のひとにも、ものおじせず、じぶんの思ったことをはきはき話して明朗快活であった。一面、これは「ナマイキ」ということでもあったが。
昭和27年、東京女子短大英語科を卒業後、舞踏家の吾妻徳穂の秘書となり、着物の知識、古典芸能、花柳界の内情に、ヨリ通じることになる。昭和31年、若いのに古風すぎると評されつつも、小説「地唄」で芥川賞候補となる。翌年に書いた「白い扇」では直木賞候補。しかし、文壇主流の賞には、以後も縁がなかった。
同世代で活躍していた美人小説家の曽野綾子とともに「才女」ともてはやされた。じっさい、頭のよさは、とびぬけていた。NHKのテレビ番組「私だけが知っている」にも2年間レギュラー出演し、テレビタレントの一面もあった。
昭和34年、明治の祖母、大正の母、昭和のじぶんとおんな三代記を物語化した「紀ノ川」を書く。有吉の作品には、その後の「香華」「三婆」「華岡青洲の妻」「出雲の阿国」「芝桜」など、はなやかな着物を来た女優の配役で、舞台化・映画化されるものが多い。辛気くさい文学賞なぞには無縁でも、うったえるストーリーで、大衆には受けた。「紀ノ川」が婦人画報、「香華」「出雲の阿国」が婦人公論と、ファッション性高い月刊誌に連載されたことは示唆的である。有吉じしん、着物を普段よりじょうずに着こなし、茶道のたしなみも深かった。
昭和34年、演劇の勉強のため、ニューヨークのサラ・ローレンス・カレッジに9カ月留学したのち、欧州に渡り、ローマ・オリンピックのようすをつたえる朝日新聞特派員のしごともしている。昭和37年、31才で、「呼び屋」の神彰(じん・あきら)と結婚したが、神の無謀な興行が失敗して大赤字、2年ももたず、協議離婚に至っている。その後、神は、「北の家族」という全国的居酒屋チェーン店経営で成功した。この間、一女をもうけている。名は玉青(たまお)。
「華岡青洲の妻」でベストセラー作家の地位を築いたのち、昭和43年、文化人類学者、畑中幸子の誘いをうけて、ニューギニア奥地へ旅行、帰国後、三日熱マラリアを発病したことがある。昭和47年の「恍惚の人」は、有吉にとって、二回目のベストセラー作となった。その後も「複合汚染」などのベストセラー作を世に出しているが、作品としては破綻しているというのが定評である。新聞連載の途絶、出版社側からの新作発刊拒否、といったことも続いている。この背景には、当時、有吉にひんぱんにみられた極度の不眠症、常軌を逸した感情起伏の激しさから判断して、躁うつ病があったのではないかと疑われている。
昭和59年(1984年)9月、自宅で突然死。享年53歳。
参考文献
1 『有吉佐和子』(新潮日本文学アルバム、第71巻、1995年)
2 関川夏央『女流 林芙美子と有吉佐和子』(集英社、2006年)
3 春日武彦『問題は躁なんです』(光文社新書、2008年)